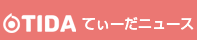県産の海ぶどうを求めて糸満市海ぶどう農園「海ん道(うみんち)」へ!
別名、グリーンキャビアとも呼ばれる「海ぶどう」。魚の卵のようにも見えますが、沖縄の海に生息する海藻です。口の中でプチプチッと弾ける食感と、ほのかに広がる磯の香りは一度口にすると忘れられず、県内外の沖縄料理店では欠かせない食材のひとつとなっています。
そんな沖縄を代表する食材=海ぶどうの養殖場『海ん道(うみんち)』が糸満市にあると知り、てぃーだ編集部が行ってきました!案内をして下さったのは、食材事業部の新垣 裕之(あらがき ひろゆき)さんです。
約 650 坪の広大な養殖場には高さ 70 cmほどの水槽が100 槽並び、その中には近くの海からくみ上げ、ろ過した海水が入っています。水温は低すぎても高すぎてもいけないそうで、「一年を通して 22 ~ 24 度ぐらいに保てれば理想的」とのこと。
「育てる上で最も大事なのは、水温と光です」と新垣さん。海ぶどうは光合成をして成長するので、太陽の光が必要不可欠なのです。そのため、曇りの日が続いてしまう冬場は管理をするのが大変なのだとか。
糸満市真栄里(まえざと)で海ぶどうの養殖場をはじめたキッカケは今から 13 年前、創業者の山城 幸松(やましろ こうまつ)さんが“海ぶどうは可能性のある食材だ”と感じたことでした。県内外だけでなく“世界に勝負できる沖縄食材を!”と、養殖業を一からスタートさせました。
海ぶどうの植え付けや選別・収穫などは全て手作業で行われるため、手間と根気が必要です。夏場は1ヶ月(冬場は2ヶ月)ほどで収穫することができるそうですが、水温や日の当たり方などちょっとした環境の変化で育ち方に影響がでてしまうため、毎日の状態をしっかりと観察しなければなりません。
さて。
みなさんはどのように海ぶどうを食べていますか? おそらく「醤油や三杯酢をつけてそのまま食べる」という方が多いのではないでしょうか。
実は、海ぶどうの食べ方はバリエーションが豊富! 養殖場に隣接しているショップでは、生で食べる以外の食べ方の提案もしています。

例えば生春巻きの具材や、ちらし寿司・パスタのトッピングにするのもオススメだそうです。

「もっと多くの人たちに海ぶどうを味わってほしいです。沖縄料理屋さんではメジャーな食材ですが、今後はフランス料理店やイタリア料理店でも使ってもらえるように、様々な提案をしていきたいです。」と新垣さん。
海ん道のイチオシは「海ぶどうアイス」。フレーバーは、宮古島の雪塩を使用したソルティーミルク、ちんすこう、シークヮーサー、アセロラ、パイナップルの5種類(2017年1月26日現在)です。
人気No.1のソルティーミルクをいただいてみました。

「アイスに海ぶどうなんて、美味しいわけが……」と食べる前は疑っていたのですが
「これは……」
「美味しい♪」
まろやかでコクのあるミルクと、海ぶどうの塩気は相性抜群!プチプチとした食感がアクセントになっていて、クセになります。
一度食べ始めると、スプーンが止まらない不思議なスイーツ=海ぶどうアイスは、全国に配送することが可能なので、お土産やお中元、やお歳暮にもぴったりですね。
そして女性のみなさんに朗報です!
海ぶどうには、美容にも効果のある生理機能があると報告されているのです。
美味しいだけではなく美肌にも良い海ぶどう。積極的に食べて、今よりも美しくなりませんか?
■海ぶどう農園のお店ぷちぷち『海ん道(うみんち)』
住所:〒901-0362 沖縄県糸満市真栄里1931 地図はこちら
電話:098-994-0016
営業時間:9:00 ~ 17:00
定休日:日曜日
Web:http://www.uminchi.com/
写真・原稿:フォトライターSachiko
Web:http://www.oishii-okinawa.com/
Web:http://www.oishii-okinawa.com/
●県産のソデイカを求めて糸満市お魚センター内にある「たらじさびら」へ!
●県産の車えびを求めて宜野座養殖場のレストラン「球屋(たまや)」へ!
OBWF公式サイト

沖縄の海は透明度が高くサンゴ礁に取り囲まれています。
沖縄県民は古くから自然の畏怖を知っています。
だからこそ、沖縄には手つかずの自然、原生林、生物の固有種が残っています。
青い空と、草木の緑と、花々の赤と、サンゴ礁の白い砂…。
色彩豊かな自然に囲まれた青い海で、沖縄の魚は悠々と泳いでいます。
アジアに近い沖縄で、OKINAWA blue water fishは育まれています。
Web:http://blue-water-fish.okinawa/
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。