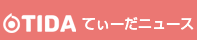【南城市】パワースポット"斎場御嶽(せいふぁーうたき)"を詳しく学ぼう!
沖縄には御嶽と呼ばれる聖地=エネルギースポットが数多く存在します。
その中でも現在でも最高霊場と言われ、
最もパワーがあるとされているのがここ斎場御嶽(セイファー)です。
現在では下の写真にもうっすら読み取れるように世界遺産に登録されています。

セイファーのある沖縄県の南城市(旧知念村)にはニライカナイ*注)伝説が数多くあります。
その中でも現在でも最高霊場と言われ、
最もパワーがあるとされているのがここ斎場御嶽(セイファー)です。
現在では下の写真にもうっすら読み取れるように世界遺産に登録されています。

セイファーのある沖縄県の南城市(旧知念村)にはニライカナイ*注)伝説が数多くあります。
海を越えてやってきた神、沖縄の始祖「アマミキヨ」が
県内のとどまった各地に史跡と由来が残されており、
それが伝説、御嶽や拝所(お祈りの場)となり
今も地元の人たちによって大切に守られています。
*注 ニライカナイとは、海の向こうにある楽園、理想郷、神の国のこと。
そこから神がやってくるという言い伝え。
そのことから戦後神社との習合がとてもスムーズに為されたと神社の神主の弁。
ここは、その海からやってきた神、
沖縄の始祖「アマミキヨ」が造った七御嶽のひとつと言われ、琉球王朝の神事の場でした。
琉球王朝では神の声を聞くことの出来るのは女性であり、
それも、王の親族の女性と決まっていました。
その女性が琉球王朝最高神官、聞得大君(キコエノオオキミ)。
その就任式もここで執り行われていました。
当時、この地は一般の人たちは入り口までしか入る事を許されず、
国王でさえ途中までしか行くことができなかった程神聖視されていました。
勿論今はどなたでも入ることが可能です。

緩やかな石の道を登っていきます。
ある箇所までは非常に重たいエネルギーを感じます。
その先へ至ると急に波動が変化して、軽やかさを増し続けます。
土地のエネルギーに疎かった私が始めて、
地熱のような大地から湧き上がるエネルギーを体感したのはこの道でした。
ここを知っている。
その感覚を受け入れた時、感じすぎるエネルギーを漸く楽しめるようになったように思います。
ここではよく、天気雨に会うことが多いのですが、
傘は必要としない気持ちの良い雨もこの石の道では、大変です。
表面に水の膜が出来るとつるつると滑るのです。
勾配も高低も大したことのない道ですが、履き慣れた靴で行かれると良いでしょう。
そして、とてもアツイです。
タオルは必ず持参くださいね。

この日はあの大打撃をこうむった台風の後ということもあり、
木々が折れたりしなったりしているのが目立ちます。
ここでは気根がかなり高くまで伸びておりその眺めは壮観です。
そこから漏れる光と、様々な光の乱舞やシャワーを見る人が多くいます。
写真に収めて帰っていらした方もいらっしゃいます。

この大量の緑から放出される生物、生命、大地のエネルギーは
身体を否応にも興奮状態に持って行きます。
毎回、細かな雨と照りつける太陽と光のシャワーを浴びて楽しみます。
この先に至るまでいくつかの神事の場がありますがそれはいつかの機会に。

この先が「サングーイ」と呼ばれる拝所となります。
白く四角く見えるのは拝所の案内だったか、由来だったかが書いてあるものです。
右側にその場所はあります。
三庫裏(サングーイ)

斎場御嶽のシンボルであり、静けさの漂う場所。
半三角形の洞門の奥の光が射し込んでいて独特の雰囲気があります。
洞門は約1万5千年前におこった地震の断層のズレからできたと言われているそうです。
幻想的な佇まいと洞門から吹き寄せてくる涼しい風に足を止めます。
下の写真はサングーイの奥。
左側は海に面した祭壇のような石段があります。

久高遙拝所(クダカヨウハイジョ)
拝所になっているとはいいがたいような、
上の写真のように珊瑚石の積み上げられた石段のようになっています。
木々が生い茂り絡み付いてそのまま伸びています。
いつもお祈りに来る人が絶えないので、
そここに線香や神様に捧げるお金の紙(黄色い紙)などが落ちていることが多いのですが、
初めて来た日は鳩がそこでのんびり寝ていたのを思い出します。
この石段の右側の景色が下。
そう、ここを眺めるための場所なのです。
久高島

この斎場御嶽から海岸へ車で2~3分の場所に安座真港があります。
そこから久高島へ向かう小さな船(フェリーか高速船)が出ています。
有名な「神の島」らしく、観光客も多く訪れます。
一日の本数も6本くらいあります。
・
県内のとどまった各地に史跡と由来が残されており、
それが伝説、御嶽や拝所(お祈りの場)となり
今も地元の人たちによって大切に守られています。
*注 ニライカナイとは、海の向こうにある楽園、理想郷、神の国のこと。
そこから神がやってくるという言い伝え。
そのことから戦後神社との習合がとてもスムーズに為されたと神社の神主の弁。
ここは、その海からやってきた神、
沖縄の始祖「アマミキヨ」が造った七御嶽のひとつと言われ、琉球王朝の神事の場でした。
琉球王朝では神の声を聞くことの出来るのは女性であり、
それも、王の親族の女性と決まっていました。
その女性が琉球王朝最高神官、聞得大君(キコエノオオキミ)。
その就任式もここで執り行われていました。
当時、この地は一般の人たちは入り口までしか入る事を許されず、
国王でさえ途中までしか行くことができなかった程神聖視されていました。
勿論今はどなたでも入ることが可能です。

緩やかな石の道を登っていきます。
ある箇所までは非常に重たいエネルギーを感じます。
その先へ至ると急に波動が変化して、軽やかさを増し続けます。
土地のエネルギーに疎かった私が始めて、
地熱のような大地から湧き上がるエネルギーを体感したのはこの道でした。
ここを知っている。
その感覚を受け入れた時、感じすぎるエネルギーを漸く楽しめるようになったように思います。
ここではよく、天気雨に会うことが多いのですが、
傘は必要としない気持ちの良い雨もこの石の道では、大変です。
表面に水の膜が出来るとつるつると滑るのです。
勾配も高低も大したことのない道ですが、履き慣れた靴で行かれると良いでしょう。
そして、とてもアツイです。
タオルは必ず持参くださいね。

この日はあの大打撃をこうむった台風の後ということもあり、
木々が折れたりしなったりしているのが目立ちます。
ここでは気根がかなり高くまで伸びておりその眺めは壮観です。
そこから漏れる光と、様々な光の乱舞やシャワーを見る人が多くいます。
写真に収めて帰っていらした方もいらっしゃいます。

この大量の緑から放出される生物、生命、大地のエネルギーは
身体を否応にも興奮状態に持って行きます。
毎回、細かな雨と照りつける太陽と光のシャワーを浴びて楽しみます。
この先に至るまでいくつかの神事の場がありますがそれはいつかの機会に。

この先が「サングーイ」と呼ばれる拝所となります。
白く四角く見えるのは拝所の案内だったか、由来だったかが書いてあるものです。
右側にその場所はあります。
三庫裏(サングーイ)

斎場御嶽のシンボルであり、静けさの漂う場所。
半三角形の洞門の奥の光が射し込んでいて独特の雰囲気があります。
洞門は約1万5千年前におこった地震の断層のズレからできたと言われているそうです。
幻想的な佇まいと洞門から吹き寄せてくる涼しい風に足を止めます。
下の写真はサングーイの奥。
左側は海に面した祭壇のような石段があります。

久高遙拝所(クダカヨウハイジョ)
拝所になっているとはいいがたいような、
上の写真のように珊瑚石の積み上げられた石段のようになっています。
木々が生い茂り絡み付いてそのまま伸びています。
いつもお祈りに来る人が絶えないので、
そここに線香や神様に捧げるお金の紙(黄色い紙)などが落ちていることが多いのですが、
初めて来た日は鳩がそこでのんびり寝ていたのを思い出します。
この石段の右側の景色が下。
そう、ここを眺めるための場所なのです。
久高島

この斎場御嶽から海岸へ車で2~3分の場所に安座真港があります。
そこから久高島へ向かう小さな船(フェリーか高速船)が出ています。
有名な「神の島」らしく、観光客も多く訪れます。
一日の本数も6本くらいあります。
・